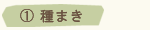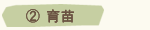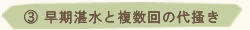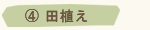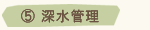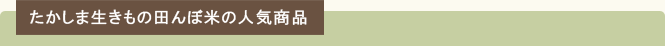栽培技術の確立
「たかしま生きもの田んぼ米」は、慣行栽培(化学農薬や化学肥料を使用する農法で、これまでは一般的な農法とされてきました)とは種まきの段階から異なる農法で育てられています。その農法の特徴をご紹介します。
たかしま有機農法研究会では、定期的に講習会を開催し、これら独自の栽培技術の確立・普及とさらなる改善に取り組んでいます。
 育苗箱(田植え機にセットする苗を育てる箱)に種まきをする際、通常の農法に比べて4分の1以下の少ない量で種籾(たねもみ)をまきます。これは、限られたスペースの育苗箱の中で、手植え時代の苗と同じ成苗(大きな苗)を育てるためです。
育苗箱(田植え機にセットする苗を育てる箱)に種まきをする際、通常の農法に比べて4分の1以下の少ない量で種籾(たねもみ)をまきます。これは、限られたスペースの育苗箱の中で、手植え時代の苗と同じ成苗(大きな苗)を育てるためです。
※田植え機が普及してから、機械で植えやすいように種を密植状態でまき、稚苗という小さな苗で植えるのが一般的になりました。ところが、小さな苗は抵抗力が弱く、雑草や病害虫に犯されやすいことが、以前に増して大量の農薬が使われる
背景となったのです。
 1箱あたり55g(通常は200g)と薄くまかれた種籾から発芽した苗を、葉が4枚半以上出るまで育てます。生長の途中で肥料が切れると苗が弱るので、大豆の煮汁などの追肥をして、注意深く育てます。この育苗の段階で農薬を使用しないお米づくりの成否の9割が決まるとも言われています。
1箱あたり55g(通常は200g)と薄くまかれた種籾から発芽した苗を、葉が4枚半以上出るまで育てます。生長の途中で肥料が切れると苗が弱るので、大豆の煮汁などの追肥をして、注意深く育てます。この育苗の段階で農薬を使用しないお米づくりの成否の9割が決まるとも言われています。
 田植えをする約1ヶ月前から、田んぼに水を入れて代掻き(土を細かく砕く作業)をします。これにより、苗を植えるより先に有害な雑草を発芽させるのが目的です。水温が20度を超えると、コナギなどの有害雑草がいっせいに発芽してきます。
田植えをする約1ヶ月前から、田んぼに水を入れて代掻き(土を細かく砕く作業)をします。これにより、苗を植えるより先に有害な雑草を発芽させるのが目的です。水温が20度を超えると、コナギなどの有害雑草がいっせいに発芽してきます。
それから再度代掻きをすることで、雑草の芽を水に浮かせたり、泥に練りこんだりして退治します。こうすることで、農薬の中でもっとも毒性の強い除草剤の使用を控えることが可能になるのです。
また、化学農薬・化学肥料不使用の田んぼで早期に水を入れることにより、土の中にイトミミズが大量に発生し、その活動で田んぼの土の表面がクリーム状に軟らかくなります。この層に残りの種子が埋め込まれ、太陽光を塞がれて発芽できなくなる効果があります。
※通常、田植えまでに合計3回の代掻きを行います。
 十分に大きく育った苗を植えるため、農薬を使う田んぼに比べて半月以上遅い時期に田植えが行われます。しかし、これが手植え時代に行われていた本来の田植えの時期なのです。
十分に大きく育った苗を植えるため、農薬を使う田んぼに比べて半月以上遅い時期に田植えが行われます。しかし、これが手植え時代に行われていた本来の田植えの時期なのです。
田植えが終わった直後に、米ヌカで作ったペレット(米ヌカを圧縮して粒状に固形化したもの)を田んぼにまきます。米ヌカが分解される過程で発生する有機酸の作用で、雑草の発芽が阻害されます。この有機酸の作用は苗の生長にも影響を与えるので、弱い苗だと枯れてしまいます。そのためにも、丈夫で健康な苗を育てる必要があります。
 田植えの後、苗の生長にともない田んぼの水深を徐々に深くしていきます。こうすることでノビエ類などの雑草が浮力によって根ごと抜けてしまうのです。十分な水深を確保するために、田んぼの畦(あぜ)を高く丈夫に設えて(しつらえて)おく必要があります。
田植えの後、苗の生長にともない田んぼの水深を徐々に深くしていきます。こうすることでノビエ類などの雑草が浮力によって根ごと抜けてしまうのです。十分な水深を確保するために、田んぼの畦(あぜ)を高く丈夫に設えて(しつらえて)おく必要があります。
水面を浮き草が覆えば、有害な雑草は日光を遮断されて発芽できなくなります。このように、自然の力を巧みに利用して雑草を抑える工夫がなされています。
順調にいけば田植え後1ヶ月には苗が大きく育ち、自ら雑草の発芽を抑える物質(アレロパシー)を発散します。こうなればもう、雑草に負けることはありません。夏の日差しを浴びて、すくすくと稲が育っていきます。